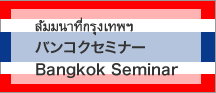新着情報
VICアカデミー 「北海道の食について ー食の魅力で地域の魅力がもっと輝くー」
2023年 01月 05日
VICアカデミーとは、弊社理念にある「学習と成長」の実践の1つとして開催しているVIC社員及び関係者のための
勉強会です。
「北海道の食について ー食の魅力で地域の魅力がもっと輝くー」
講演者:株式会社グリーンストーリープラス 代表取締役 林 真由 氏
林真由(Hayashi Mayu)
1979年 北海道帯広市生まれ
1998年 帯広柏葉高校卒業
2002年 中央大学経済学部卒業
2002年 ヤフージャパン 広告本部入社
2005年 十勝毎日新聞社 社長室入社
2015年 株式会社グリーンストーリープラス 設立
2021年 北海道チーズフェス 総合プロデューサー
資格 野菜ソムリエ/北海道フードマイスター
「北海道食べる通信」編集局長
「北海道チーズフェス」総合プロデューサー
■経歴
北海道帯広市で生まれ、中央大学を卒業後、社員がまだ500人もいなかったヤフー株式会社に新卒採用1期生として就職した。広告本部の営業に配属され、メルマガを売る新規開拓の担当になった。テレアポから始まり、知らないビルに行って、ピンポン「こんにちは」ということをする。しかし、超アナログ営業だったので、効率が良くない、と半年で部署がなくなってしまった。ただ、この時の、何の後ろ盾もないところで新規のお客さんと向き合う、という経験でついた度胸は、ビジネスパーソンとしての糧になった。
その後は花形の広告代理店営業に移った。当時はインターネット広告が底を打ったと言われる時代で、売上は右肩上がりの時だったので、目標達成300%とか、そういったことがざらだった。それを自分の能力だと勘違い。表参道にあったオフィスも六本木ヒルズに移転し、平日は毎日飲み歩いた。非常に楽しい経験ではあったが、なぜ、この会社を辞めたのか。
■転機
入社3年目ぐらいの頃、自分がやりたいことが認めてもらえず、先輩と衝突、後輩からの突き上げもあったりなど、悶々とするようになった。その頃、父が末期がんで余命半年の宣告を受けた。手術をすることになり、自分も地元に戻り、立ち会うことになった。明日この手術がうまくいかなかったら死ぬかもしれない、というような手術だったが、私がそこにいても結果は変わらないからと、母に「もう帰りなさい」と言われ、私も「そうだよね、仕事もあるし」と帰ることにした。最終便に乗り込み、畑のど真ん中にある真っ暗な帯広空港を飛び立ち、きれいな夜景が広がる羽田空港に着陸する時、自分は何を求めにここに帰ってきちゃったんだろうと、打ちのめされたような気分になってしまった。
地元に十勝毎日新聞という新聞社があるが、ここは私の曽祖父が作った会社で、叔父が社長をしていた。お正月のお酒の席で、十勝をPRするために東京で飲食店をやるぞ、とそんな話を聞いていたので、自分にやらせてくださいと手を上げた。
■お取り寄せダイニング十勝屋オープン
飲食店の立ち上げを私にやらせてくれと言ったものの、25,6歳の社会人経験もまだ3年しかない自分が、物件探しをどうしたらいいのかと考え、八重洲駅で北海道フーディストを運営していた北海道電力の担当者に話を聞きに行った。「北海道から物件を探そうなんて、甘い。自分は100件は見た」と言われ、落胆したが、まずは不動産会社に紹介してもらい、赤坂の物件を1件見て、その帰り、銀座のコリドー街というところに物件が出てるから、と言われて行ったのが2件目。まだ工事中のスケルトンの物件だったが、入った瞬間に「ここでやりたい」と思い、ここでできる気がするという根拠のない自信が湧いてきた。でもここは人気があって、「毎回100件以上の申し込みがあるからまあ無理だと思うが、試してみるのも面白いかもしれないですね」と言われ、申し込んだ。
次に、このコリドー街の物件を運営している東京高速道路株式会社に無鉄砲に何度も電話をした。いろんなことを尋ねているうちに担当者も覚えてくれて、企画書に盛り込むといいコンセプトなどを教えてもらえるようになり、ついに担当者からもお墨付きをもらえるような企画書に仕上げることができた。182件の申し込みがあった中で、最終選考の10件に残り、プレゼンテーションでこの物件を勝ち取ることができた。
2006年10月、「お取り寄せダイニング十勝屋」をオープンした。
■媒体としてのレストラン
ここまで17年間、十勝屋を続けてこられたポイントは、2点あると思っている。
1つ目は、絶対に真似されない、ブレないコンセプト。2つ目は、立地。この2つがお店が繫盛するのに必要なポイントだと思っている。
十勝屋は、十勝の食材を通じて地域貢献に寄与するとともに、生産者と消費者の架け橋になるというコンセプトを持っている。生産者のストーリーを消費者にお届けする。生産者から直送してもらった食材を生かした料理の提供、生産者を招いたイベントや通販などを通じて、生産者と消費者をつなぐ。食材の「物語」は調味料になると考え、生産者の思いを伝える場としてレストランを捉えた。レストランも、yahooや新聞と同じように、媒体だと考えている。
■日本の食の状況
日本の食料自給率はカロリーベースで38%と世界的にも非常に低い。その中で、北海道は200%を超える自給率。生産量で北海道が一位を占めるものは、生乳、乳牛、種馬、てんさい、大豆、小麦などたくさんあるが、生産額にすると宮崎が一位、北海道が三位になってしまう。北海道は食材供給で終わっており、付加価値を自ら生み出すことができていない。
また、生産者の状況を見ると、日本全体で減少しており、人口割合にすると1.3%にまで落ち込んでいる。さらにその1.3%の人たちの平均年齢が67.8歳。65歳以上が68%で、日本の将来はあるのか、というような状況。北海道も同じような状況になっている。漁業においても生産人口が減少している。
都市と地方との分断も大きくなっている。北海道の中でも、たとえば札幌市の自給率は実は1%。人口は増えているが、生産地が減っている。また、自分も十勝帯広にいた頃は、農家さんの知り合いや同級生、父が生きていた頃は、その人脈もあり、夏になったらトウモロコシ、秋になったらジャガイモ、鮭をまるごと一本もらったらイクラを作る、というのが風物詩だった。しかし、歳を重ね、父も亡くなると、そういう付き合いがどんどんなくなってしまい、やはり生産者との分断ということを感じている。
■『北海道食べる通信』
私は買い物は将来に向けての投票だと思っている。将来残ってほしいものにお金という票を投じることによって、生産者が残っていく。そんな思いで始めたのが「会いに行きたくなる食物語」というコンセプトの『北海道食べる通信』。この雑誌は3,980円。生産者の食材と、その生産者を特集した記事が載った情報誌がセットで届く。生産者を知らないと投票はできない。食材のストーリーに「共感」してもらうことが必要。そして、実際に食材が届いたら、今度は消費者に「こんなふうにおいしく食べましたよ」という投稿をしてもらう。
そうすることで、生産者にモチベーションを還元できる。消費者は買い物することで、日本の食を守ることに「参加」ができる。「共感」と「参加」がキーワードだと思っている。
私自身が、取材を通じていろんな生産者を知って、その食材や商品を応援したいな、という気持ちになった。
トウモロコシの種を毎年、自分で作っている生産者がいる。通常はアメリカからの輸入で、種から作る人は1%もいない。しかしアメリカが輸出を禁止したらどうなるのか。またこの生産者が作った種はきれいな黄色だが、輸入の種には薬が塗られているため、赤い色をしている。
甘海老の漁師は、大しけの海に出て船の低い柵のところで、エビが入った籠を引き上げる。利尻島の利尻昆布を採る漁師、この漁も実は過酷。力づくで海から引き揚げて、家族総出で干していく。五味(甘味・酸味・塩味・苦味・旨味)のうちの旨味は、日本人が昆布から見つけたものだ。
■北海道チーズフェス
もともとチーズが大好きだったが、2005年、十勝毎日新聞社でチーズの国際会議を誘致した際、すごい種類のチーズが並ぶ中で、北海道のチーズは、白カビかゴーダチーズくらいしかなかった。
2021年、十勝毎日新聞社が主催してチーズイベントをやろうとしたが、コロナで開催できなくなった。「チーズは集めるのにもったいない、どうしようか」と相談されて、オンラインで売ることにした。ミモレット、モッツァレラ、白カビ、青カビ、ハード系のチーズ、味噌のついたオリジナルのチーズなど、ありとあらゆる種類のバラエティ溢れるチーズを集めることができ、北海道チーズ50種類食べ比べという形で400名に発送した。
この成功経験を踏まえて、今年もイベントを実施した。日本人のチーズ消費量は増加傾向にあるが、実はそのうちの9割が輸入で、国産は1割にも満たない。2006年頃、全国のチーズ工房は100件ほどだったのが、現在は330件を超える。まだまだ伸びしろがある。輸入が9割というところに風穴を開けていきたい。そこでも「共感」と「参加」がキーワードだと思っている。チーズ工房をもっと知ってもらわないといけないと感じ、ポケットマルシェという、生産者から直接食材を買えるアプリを運営する会社(いわばライバル)に、「チーズの生産者を応援しなければ」とプレゼンテーションをして、『にっぽんのチーズ定期便』というサブスクを作ってもらった。
■今後の野望
次にやりたいこととして、北海道の食材を広げていくために世界も視野に入れなければ、と考えている。北海道出身である自分は本当にラッキーだと思っているから、北海道の食を日本だけでなく、世界にPRする仕事をしていきたい。